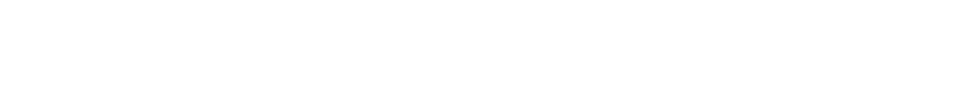少子高齢化が進む中、家族による介護には限界がきている現状があります。
とくに認知症の方の介護では、想像を超える心身の負担がかかることも多く、介護うつや介護離職という深刻な問題にもつながっています。
この記事では、私自身が経験した「父の介護」と向き合った日々を振り返りながら、家族介護のリアルな現状と、少しでも介護者の心が軽くなる方法について綴ってみたいと思います。
家族介護が抱える問題とは?
3世代同居は減少、介護の担い手は少なく…
現在、65歳以上の高齢者がいる世帯では、以下のような変化が見られています。
- 3世代同居が減少し、夫婦のみの世帯や単身世帯が増加している
- 要介護者がいる家庭でも、3世代ではなく夫婦二人きりや一人での介護が増えている
つまり、家族の力だけで支える介護には限界がある時代に入っているのです。
家族介護がもたらす5つの負担
私が実際に経験して感じたのは、介護というのは体力だけでなく心のスタミナも必要だということでした。主な負担には、以下のようなものがあります。
- 身体介護による肉体的疲労
- 夜間の見守りや対応による睡眠不足
- 同居家族への精神的・時間的大きな負担
- 先が見えず終わりのない介護で、ストレスや不安が溜まりやすい
- 特に認知症介護では暴言・妄想・徘徊などに悩まされ、昼夜問わず休めない
こうした状況が続くことで、介護うつになる方も少なくありません。
私自身が経験した「父の介護」の日々
2年前、私は実父の介護に直面しました。
きっかけは、母が交通事故で入院し、父の介護を担える人が急にいなくなったことでした。
父は膀胱がんのターミナル期。
私はその頃、長年の夢だったカウンセラーとしての起業を控えていましたが、すべてを一旦ストップせざるを得ませんでした。
看護師として働いていた経験から、介護認定の手続きや制度の活用にはある程度スムーズに対応できましたが、現実はそんなに簡単ではありませんでした。
- 父は訪問看護やヘルパーの利用を拒否し、説得にとても苦労しました
- 医療や介護のサポートがあっても時間的制限があるため、結局は家族が支える部分が多い
- 30年以上別々に暮らしていた父と急に同居する生活は、想像以上に過酷でした
介護を【ひとりで抱えない】ために大切なこと
この経験を通して私が強く感じたのは、「介護をがんばりすぎないこと」「話せる相手を見つけること」の大切さです。
介護者も人間です。疲れて当然、つらくて当然なんです。
時には「誰かにただ話を聞いてもらいたい」「自分の気持ちを吐き出したい」そんなふうに感じることも多いのではないでしょうか。
介護の悩みに寄り添う存在として
私は、自分の介護経験と看護師としての知識・視点を活かしながら、
介護に悩む方の声に耳を傾け、少しでも心が軽くなるようなお手伝いができればと思っています。
- 愚痴を聞いてほしい
- 介護の相談をしたい
- 制度やサービスの使い方を知りたい
どんな小さなことでも大丈夫です。
「誰にも言えない気持ち」をひとりで抱え込まずに、まずは話してみませんか?
おわりに|介護する人も、笑顔でいられるために
介護は、誰にとっても突然始まることがあります。
そして、「大切な家族だからこそ、つらい」という矛盾を抱えてしまうものです。
だからこそ、介護する人の心のケアがもっと大切にされる社会になることを願っています。
私もその一助となれるよう、これからも寄り添い続けていきたいと思っています。